サイクルスポーツの編集長が某Youtuberになったことが少し話題になった。数ヶ月限定で編集長が変わっていくらしい。ということで自分がサイスポ編集長になったら何やるか?っていうのを考えてみた。
- 105ヒルクライムのおすすめ記事集
- ホイールの慣性モーメントのデータ
- スポークの空気抵抗の影響はどれくらいか?ディスク化のデメリット
- 慣性モーメントやエアロスポークの実際のワット数の変化はどれくらいなのか?
- 横風のハンドリングへの影響に関する考察
- ホイールの剛性と踏みやすさについて
- トレール値について(特に登りのシャキシャキ感に大きく影響する)
- タイヤの太さとトレールの関係
- エアボリュームによるサスペンション効果について
- 速く走れる太いタイヤとはどれなのか?
- フレーム設計について、設計者が何を考えて制作しているのか?のインタビュー
- チューブレスタイヤのためのシーラントの重量
- グラベルバイクのポジションの目安とセッティングのやり方
- ロードバイクのシフト方法で、メジャーブランド(シマノ、SRAM、カンパ以外)の可視化とインプレ
- ブレーキレバー特集
- ロードバイクのギア比の選択について
- ミドルグレード以下のバイクのインプレ特集
- 各SPDシューズでどこまで歩けるか
- 印象的だったアイテム類の記事
- あんまり知られてないかもしれない季節と体調の関係
- まとめ:以上、105ヒルクライムのおすすめ記事集でした。
105ヒルクライムのおすすめ記事集
自分が編集長になったらやる特集って言っても、気になることは基本的に調べてこのブログに書いてる。改めて自分が編集長をやるとしたら、このブログの内容を専門家や他のライダーにもインプレをもらったりしてさらに深く検証する内容になるだろう。

つまりは 105hillclimb の特選記事集というわけですね。ということで以下、おすすめ記事をまとめてみました。
ホイールの慣性モーメントのデータ
ホイールを購入するときに気になることといえば、25mmの軽量リムと50mmの重めのリム、どちらが速いのか?その違いってどれくらい影響が出るのか?

これを知るために、リムの「慣性モーメント」を計算しました。加速で必要な出力はその数値に比例するはず。この表と照らし合わせて、自分の納得できる慣性モーメントのホイール(例えば今のホイールより慣性モーメントが小さいもの)を購入すれば、その点において失敗はないでしょう。
スポークの空気抵抗の影響はどれくらいか?ディスク化のデメリット
当然ですが軽いリムが「慣性モーメント」では有利。しかし空気抵抗はリムハイトが高い方が有利です。じゃあ、どれくらいリムハイトで空気抵抗は異なるのか?スポークが空気を切断する抵抗を計算してみようというのがこの記事です。こちらも自分の納得できる空気抵抗係数以下のホイールを選べば、高速域で漕ぎが重い・・・というような失敗はなくなります。気をつけたいのはリムブレーキからディスクのバイクに買い換える時。スポーク数が多くなるので、これまでよりもリムハイトを高くする必要があります(私はこれで思ったより高速域で伸びない・・・という失敗しました^^;)。
慣性モーメントやエアロスポークの実際のワット数の変化はどれくらいなのか?
では、上で調べた「慣性モーメント」と「ワット数」の関係はどうなっているのか?実際の実験データと照らし合わせてみました。
横風のハンドリングへの影響に関する考察
リムハイトが高くなると、横風の影響が出てくる。急にハンドルが取られるのは怖いですが、最近のリムは進化していて、リムハイトが高いホイールのほうが、低いホイールよりも横風の影響を受けないケースもある。それについて考察しています。
ホイールの剛性と踏みやすさについて
では、以上の条件を満たすホイール(外周が十分に軽く、かつ空気抵抗が低いホイール)であれば、絶対に満足できるホイールなのか?答えはNOです。例えば、レーシングホイールは硬くて踏み続けられないことがある。私の場合、BORA WTOでそれを体験しました。そんなわけで、ホイールのインプレッションには「踏み続けやすさ」という評価項目を追加してほしいと思っています。(今は無き La route でその試みがありましたが・・・)

で、BORA ONE と BORA WTO の踏みやすさって全然異なるので、何が違うのか?についても考察したことがあります。
また、BORA ONE よりも踏みやすいホイールがあり、それは BERDスポークのASTUTOでした。
デイスクのホイールで言えば、踏み続けやすさ ASTUTO EV36>TOKEN Roubaix>=BORA ONE>ZIPP303s
リムブレーキのホイールだと、
レーシング7>=キシリウムエリート>コスミックカーボンUST>シャマル>BORA WTO 45

っていう評価になります。ホイールの硬さって好みがあると思うので、これを雑誌などのインプレで書いてくれると、ホイール選びの一つの指針になるでしょう。(※試乗時のスポークテンションも合わせて書く必要があると思いますけど)
※これらのホイールについて、詳しくはここに書いています。
トレール値について(特に登りのシャキシャキ感に大きく影響する)
自転車にとって大事なことにジオメトリーがあります。個人的に重視しているポイントはトレール値。ヒルクライムのときのバイクの振りやすさには、トレール値が大きく関係するように感じます。特に身長170cm以下の小さいサイズでは注意しないと、うまくダンシングが出来ないフレームが存在する。
ここにも書いたけど、トレール値が大きいとダンシングでハンドルとペダルのタイミングが合わせづらかったりする。※少なくとも自分にとっては
もちろん合わないときはシッティングで淡々と回せばいいんだけど、自分の登り方にぴったり合うトレール値が存在するかもしれないということは知っていてもいいと思う。

タイヤの太さとトレールの関係
タイヤを太くしてもトレールは変化する。グラベルバイクや、昨今のタイヤが太く、オールロード化しているロードバイクでは気にした方が良い。バイクの購入時に気にしたいトレールの話。グラベルバイクでは、トレール値が全く異なる設計の4台のバイクを例としてあげているので、バイク選びにも参考になると思います。
エアボリュームによるサスペンション効果について
タイヤを太くすると、サスペンション効果で荒れた路面でも速く走れるようになる。砂利道だと明確なアドバンテージになるし、太いタイヤってとても楽しい。40c以上の太さから楽しさが一気に増してくる印象。45cもおすすめできる。
この「エアボリューム」VS「トレール値&軽量さ」っていうのは、空気抵抗の低い「リムハイトの高いホイール」VS慣性モーメントの小さい「ローハイトホイール」のような「メリットが両立しない」構図でもある(あるいは上のトレールの記事内になるように、フレーム選びから対処する)。ライダーはこのことをよく知っていれば、自分の求める自転車を見つけるのが容易になるかもしれない。

速く走れる太いタイヤとはどれなのか?
グラベルバイクって、ロードバイクよりももっさりすると思っていたら、実は思うほどでも無かったりする。実はMTBタイヤに驚くほど転がりの軽いタイヤが存在する。
こんなタイヤと、トレールの短いグラベルバイクをあわせて走ったらロードバイク要らないなんてならないだろうか??データだけでなく、ライダーによるインプレをしてもらいたいところ。
ちなみに、KAHAに試乗したときにブロックタイヤを履いているのに並のロードバイクよりシャキシャキして速いと感じました。
フレーム設計について、設計者が何を考えて制作しているのか?のインタビュー
ロードバイクって新型が発売されると、◯ワット削減とか、剛性◯◯%アップって謳い文句がよく使われます。しかし、それらは何かを求めた結果生まれた成果である。だから、数値の前に、フレームの設計者が何を目指して、どんなアプローチで、前作からどこを改良しようとしたのかって詳しいインタビューを聞きたかったりする。
そんな話を CHAPTER2 のマイクプライド氏に聞けたので、それを書きました。
これは本当はちゃんとした自転車ライターの方に書いてもらいたいような記事でした。
チューブレスタイヤのためのシーラントの重量
さて、ここからは細かいことだけど、シーラントでタイヤがどれくらい重くなるのかの検証。MAKUHALは軽いと言われているけど、その他のシーラントでどうなのか、データを見たことある??カフェラテックスと、スタンズでは結構異なるし、MAKUHARUでなくても、5gくらいしかシーラントで重くならない方法もある。
グラベルバイクのポジションの目安とセッティングのやり方
グラベルバイクを購入するときに、これまでのバイクとスタックとリーチが異なるのでどれを買っていいのかわからない!なんてことはないだろうか?よく「フレームはスタックとリーチで選べ」って言うけど、根本的な設計が異なるバイクだと基準がないから選べない、という問題がある。そんなわけで、メーカーの完成車で同じサイズならどれくらい、ロードバイクとグラベルバイクでハンドル位置が変わるのか調べてみました。
実際の運用では、ロード基準でハンドルポジションを出すというより、「未舗装路で8の字を描いてみる」というやり方のほうが、扱いやすいハンドルポジションに合わせられると思います。
このやり方なら、ロード基準で合わせていくと、解決しない問題を解決することが出きます。

ロードバイクのシフト方法で、メジャーブランド(シマノ、SRAM、カンパ以外)の可視化とインプレ
ロードバイクのシフト方法の特集。シマノやSRAM、カンパという特集はされるけど、それ以外のWHEELTOPやクラシファイド、ギブネールやダブルレバー&ウイングシフターの比較をやってもいいでしょう。特にコンポの価格も値上がりしているので安くていい方法があればその方がいい。
ボタン式の電動変速は機構的に非常に優れていると思います。特にケーブルがなくなることよりも、フロント周りを劇的に軽量化することが出来るメリットが大きいと思います。
試乗したWheelTopはフロント変速が今ひとつ。リアだけなら満足できると思う。
フロントディレーラーよりもクラシファイドのほうが優れているけど、やっぱりホイールに依存するという大きなデメリットもある。
電動でない場合も様々な変速方法がある。
フリクションシフトも実際に使うと全く悪くない。

シマノの機械式変速の代わりにSENSAHを使うのだってアリだ。
ブレーキレバー特集
シフトがシマノやカンパなどから開放されれば、ブレーキレバーを自由に選ぶことが出来るようになる。ブレーキレバーによってブレーキのフィーリングは大きく変わる。手が小さい人にはとても大切。ブレーキャリパーを選ぶようにブレーキレバーだって選べるといい。
ロードバイクのギア比の選択について
旧来のロードバイクってノーマルクランクに25Tなんかがついていて、とても坂なんて登れたもんじゃなかった。そんな中書いた、俺達にはギア比1が必要なんだよ!という記事。今やシマノがギア比1を実現するコンポを作っているし、コンパクトクランク×11-32t みたいなバイクが標準で売られるようになってきました。重要性は減りましたが、軽いギアの必要性について、改めて。
ミドルグレード以下のバイクのインプレ特集
雑誌では、ハイエンドバイクの特集は売れて、ミドルグレードのバイクを特集しても雑誌は売れないと聞いたことがある。だからミドルグレードの特集はほとんどされることがなかった。しかし、バイクの試乗記事で私が一番おもしろかったのはミドルクラス特集でした。※サイスポのこの号です↓
吉本さんと安井さんが、各社のミドルグレードに乗って、どこが弱点でこれを変えれば良くなるなんて書いてる。最終的に予算を決めてそれぞれがオーダーするバイクを決める。という記事なんだけど、これこそがいまの価格高騰しているディスクブレーキ・バイクに必要なんだと思う。
グラベルバイク欲しくて、私的に安く組んだ例はこちら。今ならフレームにCRUX DSWあたりを選ぶかもしれません。
ということで、そんなに高くないのにいいと思ったバイク・インプレ集
参考までに
各SPDシューズでどこまで歩けるか
最近ロードバイクにSPDペダルを付ける人が増えているという。ただ、SPDペダルも様々な種類があり、シューズだって多様な種類がある。じゃあ、SPD-SLからSPDに変えたときのメリットとデメリットはどんな感じなのか?SPDにシューズだとどんなふうにサイクリングライフが変化するのか?こういういった話を書いてみるのもいいだろう。

以下の記事ではシューズによってどこまで歩けるのか?ってイメージが湧くと思う。軽登山靴レベルのSPDシューズを履けば、バイク&ハイクのイメージだって湧くかもしれない。
印象的だったアイテム類の記事
非常に印象的だったケミカル。パークツールの滑り止めスーパーグリップコンパウンド。地味ながらよく効きました。最近の専用シートポストのズレ下がりや音鳴りに悩んでいる人には参考になるかもしれません。
MKSペダルは一発でファンになりました。SPD-SLの代わりにはなり得ないけど、非常に感銘を受けるパーツであります。回転が良すぎて、乗るたびに快感を得られる稀有なパーツの一つ。
トムソンのクランプもとても良かった。完成車についてるメーカー製のクランプって完璧ではないことがあるし、シートクランプって結構違うんですよ。
専用品だと選べないけど、本当はクランプだって色々あるし、選びたい。
雑誌なら絶対にかけないと思うけど、よくある故障とその対策について
あんまり知られてないかもしれない季節と体調の関係
ヘマトクリット値が自転車の能力に影響することは知られていると思うけど、ヘマトクリット値が季節によって増減すると言われていることは知られていないかもしれない。
まとめ:以上、105ヒルクライムのおすすめ記事集でした。
自転車をやっていて、雑誌などを読んでいてもわからないこととか、言及されていないことについて気になって考えてしまう。これらの記事は、自分が考えたことを忘れないために書いている。誰かに伝えるために書こうとすると、考えがまとまってくるというメリットもある。

まだ自分自身気になるけどよく分かっていないことだってある、例えば、低圧にしたときの摩擦についての考察(ヒステリシス摩擦とタイヤ表面の摩擦について)。
これだけ書いておいて、本当に自分が言いたいことは、ロードバイクだってグラベルにいけるし、軽いギアを付けて、高剛性過ぎない走りやすいホイールを履いて、携帯リュックと輪行袋を持って、好きな方向に向かって走るのって楽しいよ!ってことくらい(追い風だったらなお最高!)。

最後に房総半島のライドをおすすめしておきます。
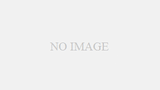

最近の自分はこういうライドが好きな人です↓





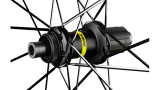
























































コメント